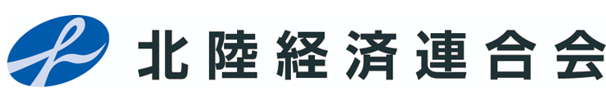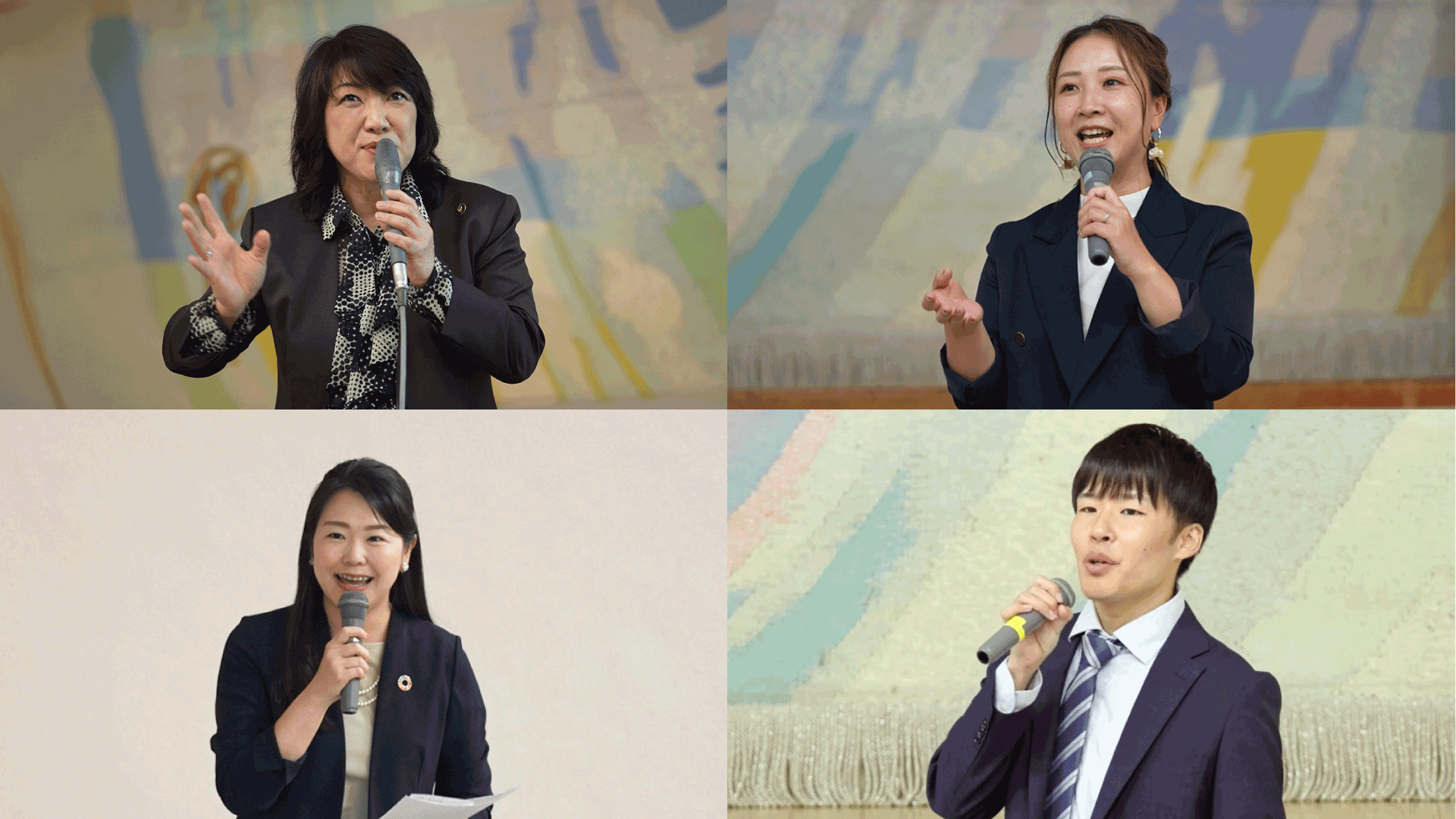敷島製パン株式会社の工場長として、赤坂さんは女性リーダーシップの可能性を広げてきました。管理職として日々の課題を乗り越え、ご自身の強みを見出す挑戦を続けている赤坂さん。株式会社ワーク・ライフバランスの大塚万紀子との対話を通じて、変革を求める企業にとっての指針となる彼女の歩みを描きます。
工場長としての挑戦
――まず、工場長の打診を受けたときの気持ちや状況を教えていただけますか?
赤坂様(以下、赤坂):聞いた瞬間は、「えっ?」と、とにかく驚きました。
当時、そろそろ別の工場への異動もあるかもしれないと思っていた時期でした。そんな時に突然、統括部長から電話がかかってきたので「ああ、人事の話だな」と。でも、なぜ直属の上司である工場長でなく統括部長から電話が来るのだろう?と内心穏やかではありませんでした。
「(埼玉の)工場長だから」と言われた瞬間、全く理解が追いつかず、「なぜ私が?」という気持ちでいっぱいでした。女性、そして間接部門である総務から工場長は無理があるのではとも思いました。
――その後、どうやって気持ちを整理されたのでしょうか。
赤坂さん:正直、当時は毎日「どうしよう、どうしよう」と思っていました。
でも、夏休みに帰省した時に父が「大変だと思うけど、部下の管理職を大事にしろ」と言ってくれたんです。他にも励ましの言葉をくれ、応援されていると感じて、「(この人事が)変わらないのであればやってみよう」と思えるようになりました。
管理職を経験したことのない父からの意外な言葉が大きな後押しになり、2022年9月1日から工場に入りました。
――それくらいのタイミングで、弊社がサポートさせていただくことになったのでしたね。工場長になられて感じた課題や、大変だったことは何ですか?
赤坂さん:周りの取締役クラスの方々は「マネジメントだから大丈夫、やれるよ!」と言ってくれました。でも、現場の人間にとっては「俺についてこい」というスタイルの方が楽だったかもしれません。
私は「分からないから教えて」と聞けるようなスタイルが良いと思っているので、声を掛けたり聞いたりしながら、少しずつ変わっていけたらいいと思いました。1カ月、2カ月で変わるとは思えませんが、続けていくことが大切だと。
 左:敷島製パン株式会社埼玉工場 右:赤坂工場長
左:敷島製パン株式会社埼玉工場 右:赤坂工場長
工場長になった1年目は、とにかく自分流でやってみるしかないと思いました。
1年目はとにかく記憶がほとんどなく、現場を回ることで精一杯でした。似たような審査や監査が多くて、「あれ、これのときはどうだったっけ?」と迷うことも多かったです。ラインの稼働時間や製造数などの数字を把握するプレッシャーもありましたが、製品が変わるたびに、新たに数字を把握し直す必要がありました。なかなか頭に入らなくて苦労しましたね。
2年目は業績が良くて、「埼玉(工場)調子いいね」と言われることもありましたが、甘んじてはいられないと思っていました。
いろいろな製造に関する会議で「この数字はこうだからこういう結果」というのが、やっと3年目で分かるようになりました。分からないと何も言えないし、聞けないんですよね。総務のことなら自信を持って話せますが、製造側は経験も自信もなくて。それが3年目になってやっと少し分かってきたところです。

ダイアログと自己成長
――弊社が管理職、特にエグゼクティブの皆さんに向けてご提供する6カ月間の育成・ダイアログプログラムに参加いただきました。そこでは赤坂さんの個性について、かなり時間を割いてお話しましたね。
赤坂さん:特に印象に残っているのは、まず、大塚さんに「誰を赤坂さんの成長の味方にしたいですか? 誰と話したいですか?」と具体的に尋ねられたことです。その時は営業部長の名前を挙げました。
そして「営業部長と何を話しますか?」と深掘りしていただいたことが印象的でした。それまで、誰と話すかは考えていましたが、どういう話をして、何を目的にするかを強く意識しました。
個人的には、自己理解のアセスメントを活用したことが大きかったです。自分ができていない部分や足りない部分を知り、戦略・戦術的な面を伸ばしたいと思っていましたが、今ある強みを伸ばしつつ、人に頼るという発想を得られたことが印象に残っています。
私は特に課題の発見と、問題を突き止めたい、課題を解決したい欲求にもとづいて行動することが強みだと気付きました。工場で、真っすぐでないものを真っすぐにしたい、人を助けたいというのはこれだなと。これは私の強みなので、自信を持って仕事を続けたいと思います。
――マイナスをゼロの状態に戻す力、そこから飛躍するための準備力がある、ということですね。何かがマイナスになってしまったり、ゼロに達していないときに、赤坂さんはすぐに気づいて、声を掛けたり対策を打ったりして、ニュートラルな状態に戻してくれますね。 私たちのダイアログでは対話を通じて具体的な課題解決に取り組みましたが、いかがでしたか?

赤坂さん:1対1の贅沢な時間でしたし、自分の頭で考える問いもありました。それが自分の弱点で、一生懸命考えることが仕事の外でできたのは良かったです。
仕事をベースにしながらの対話ですが、良し悪しや点数が付けられる心配がないので、自由に発想したり、経験を振り返ったり、未来を予想することができたように思います。気づいたら1時間、1時間半と時間が経っていた、という感じでしたね。あっという間でした。
――赤坂さんが工場長になって3年が経ちましたね。最初の頃にご一緒したセッションが、今お役に立てていると感じることはありますか?
赤坂さん:御社のセッションでは、「問い」がとても印象に残っています。「赤坂さんはどうしたい?」と問われて、そこで初めて自分の望みを考えました。
質問を重ねることで、最終的に自分がまず何をすべきかが見えてくるんですよね。これは、製造に関する会議でも役立っています。何が目的で、何をすべきなのか原点に立ち返るために問うことをしています。
目的達成がうまくいかないのは時間がないからなのか、スキルが不足しているからなのかなど、原因を探ることが大切と感じています。
――「どうしたいのか」というのは、内発的動機に関わる部分ですね。自分の内側から出てくる動機は、最もパワフルで持続性があります。特に工場長という立場では、赤坂さんご自身の内発的動機が強くないと、皆さんを引っ張っていくのは難しいですものね。
赤坂さん:セッションを受けて自分に足りないと感じたのは、人のモチベーションを上げたり、人をやる気にさせたりする方法です。手法は理解しても、誰にどのように応用するかが難しかったですね。
――赤坂さんは総務出身ということもあり、そういう分野に関心が高いと思っていました。ご自身の興味・関心のある分野は今の仕事に生かせていますか?
赤坂さん:成果というほどではないですが、コミュニケーションを大事に思っていて、どんな人とでも話せるようになりたいので、それを実践し、仕事での気付き、人の良い面や特技が引き出せたらと思っています。話をしていると「そんな特技や考えがあったの?」とか「そんなことに気をつかっていたの?」と驚くこともあります。こういったことを上司に伝えて、本人を褒めたり、理解してもらうようにしています。

――一緒に工場長心得も作成しましたね。そのプロセスで何か気づきはありましたか?
赤坂さん:もともと、こういうものを作るのが大好きなんです。以前、別の工場にいたときは、自分がいなくなったときのために、業務の締め切りや必要なリソース、報告先などをまとめていました。
工場長の心得を作ったときも、同じように自分がいなくなった後に役立つようにと思い、今後アップデートされることも期待して作りました。
――手引きを作る過程で「これは必要だけど知らない」とか「どこにあるのか分からないから調べなきゃ」とおっしゃっていたのが印象的でした。手引きを作る中で、知っていることと知らないことの整理が進んだのではないでしょうか。
赤坂さん:そうですね。月間や年間の予定をまとめると、自分の弱点が見えてきます。例えば、審査で社外の方が来たときに「この1年で工場が変わったことは?」と聞かれても、変わりすぎていてすぐには出てこないんです。工場長として即答できるよう用意しておかなければと思いました。
手引きを作ることで、自分の弱点が浮き彫りになりましたし、工場長としての意識も高まったと思います。「やるべきことがたくさんあるな」と実感しました。
組織におけるダイバーシティの重要性
――では改めて、工場長として勉強になったことは何ですか?
赤坂さん:他のリーダーの考え方にも興味を持つようになりました。いいとか悪いとかではなく、そういう考え方になったのは大きな変化です。
役職が上がると、情報量も増え、自分の指揮者としての考え方を訓練することが必要だと感じています。テレビを見ながらニュースとなっている事象を工場で起こったことと置き換えて考えるのも訓練だと思っています。
次世代のリーダーに伝えたいこと
――次の世代の工場長、これは女性に限らず男性も含めて、若い方が工場長になることもあるでしょう。そのときに、どんな声を掛けたいですか?
赤坂さん:サラリーマンとして、上の考えや経営方針に沿って行動することになりますが、それとともに、自分はどう生きたいのかを常に考えてほしいです。
人生には限りがありますから、それを充実させるためには、今の仕事を続ける先に何を見出すのか、あるいは早いうちに違う働き方や人生を見つけるのかを常に考えてほしいですね。
そして、若い人たちには、ぜひ自己研鑽に励んでほしいと思います。自己研鑽を通じて、経験値を積み重ねることができれば、たとえ突然工場長のような重要な役職に就くことになっても、「準備ができていた」と思えるような自信や悟りを持てるかもしれません。
ずっと同じ状態で満足していると、予期せぬ変化や新しい人生の局面に直面したときに対応が難しくなることもあります。ですから、そうした変化に備えて、常に学び続けることが重要です。
課長になる前のアセスメント研修を初めて受ける営業職の女性にも、「どんな機会でも積極的に活用した方がいい」とアドバイスしたことがあります。私は、何でも気軽に質問してもらって構いませんし、皆さんを全力でサポートしたいと思っています。
新しいことに挑戦することは、必ずしも簡単ではありませんが、その過程で得られる知識やスキルは、将来の大きな力になるはずです。
WLB大塚:失敗しても、それが糧になりますものね、必ず。人事の塚本さんにお伺いしたいのですが、今回のダイアログをやろうと思ったきっかけは何だったのですか?
塚本さん:初めての女性工場長ということで、赤坂さんもいろいろ苦労されるだろうなと思っていました。それに対するサポートができたらと考えたのが一つの理由です。
もう一つは、これが終わりではなく、ここからがスタートだと思っています。今後、赤坂さんの経験を活かして、次世代のリーダーがスムーズに成長できるよう、具体的なサポート体制を整える必要があると感じました。
赤坂さん:会社が成長していくためには、性別に関係なく、すべての従業員が働きやすい環境を整えることが何よりも重要です。特に、サポートを必要とする人々にとって、安心して働ける環境を提供することが、企業全体の活力を高める鍵となります。
私自身、大変な状況に直面しながらも、今まで話したことのない人々と新たな関係を築き、これまで経験できなかったことに挑戦する機会を得てきました。このような経験を通じて、視野を広げ、多様な価値観を理解することができたのは大きな財産だと思っています。